和泉式部と雨宿りの栗の木
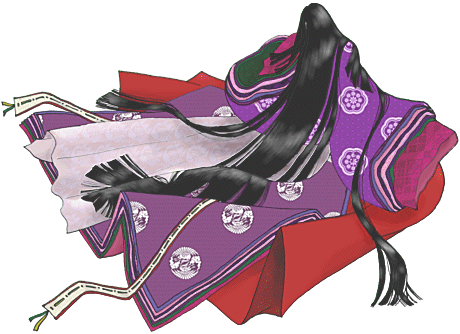 |
時は平安中期、絶世の美女で和歌を詠む才能に |
| 式部は少女に「その綿、売るか?」と問いかけました。すると少女は 『秋川の瀬にすむ鮎の腹にこそ うるかといえる わたはありけれ』 と和歌で答えました。しゃれの効いた歌に感心して 「あな子女が良くよめたり!」と褒めたところ、『秋鹿の母その柴を折り敷きて 生みたる子こそ子女鹿とはいえ』と、また しゃれの効いた歌で答えてきました。いよいよ感心した式部は五郎太夫に「この賢い子は誰の子か?」とたづねたところ 十数年前に都でひろった子だと答えました。五郎太夫がひろったときに少女が着ていた着物と持たせた薬師如来像から、 昔すてた自分の子だと式部は確信しました。和泉式部が肌身離さずもっていた布と産着の模様も合い、産着の紐 には『捨てし子を誰とりあげて育つらん 捨てぬ情を思いこそすれ』と式部の歌も書いてありました。 娘を返してもらった和泉式部はかわりに薬師如来像を五郎太夫にあずけ、娘と共に都へ上りました。 娘も母の和泉式部と同じく、中宮・彰子に仕え、小式部内侍と呼ばれ歌人として活躍しました。 |
|
※『苔むしろ 敷島の道にゆき暮れて 雨の内にし 宿る木の影』 広い日本の誰も通らない苔が生えた様なところを あてどもなく歩いて、探すものも見つからず、雨にも降られて今、木の下で雨宿りをしている ※『秋川の瀬にすむ鮎の腹にこそ うるかといえる わたはありけれ』 川にいる鮎のおなかにウルカ(鮎のはらわたを 塩漬けにした珍味)というワタがありますよ ※『秋鹿の母その柴を折り敷きて 生みたる子こそ子女鹿とはいえ』 こめかとは、母鹿が苦労して集めた柴をしいた上で 生んだ子が本当の子女鹿(こめが)ですよ ※『捨てし子を誰とりあげて育つらん 捨てぬ情を思いこそすれ』 捨てた我が子を誰かがひろって、子は育っていくだろう しかし子を思う愛情は捨ててはいないと思ってくれるだろうか 追記 この相生市に伝わる和泉式部の物語は多くの郷土史や本に出てくる物ですが、実際に小式部が仕分けていた綿は 平安時代には、まだ普及しておらず、綿といえば絹の綿で、木綿の綿は室町以降の様です。時代が経つにつれて絹と木 綿がとってかわったのかもしれません。 | |
| 和泉式部のよく似た伝説は全国各地に残っていますが、栗の木が登場するのは 相生市にのこる伝説だけです。 その栗の木は現在の相生市若狭野町雨内(あまうち)にありましたが、枯死してしまい 今はかわりに植えられた栗の木と石碑があります。 石碑は厳選に厳選をかさね、米粒の形をした石を選び、となりの矢野町瓜生(うりゅう) から運び大正4年8月に雨内の村人の寄付でたてられたそうです。 米粒の形にこだわった理由は雨内と言う土地が米が採れ難く、苦労して開墾した土地と いう事にあるようです。 これは稲垣公廟祭につながっています。 和泉式部を庇った栗の木は倒れた後も、村人が磨き大切にされていたようです。 |
 |
|||||
| 雨内の栗の木は枯れてしまいましたが、移植されたものが相生市那波にある得乗寺 (とくじょうじ)に今もあります。樹齢は600年とも700年ともいわれています。 昭和10年に県天然記念物に指定されました。 ここまで枝が枝垂れている栗は日本広しとも、ここにしかありません。 雨内にあった栗の木が何故、海に近い那波にあるのかは諸説あり、その昔、雨内の 教証寺(きょうしょうじ)の住職と那波の得乗寺の住職が栗の木を賭けて碁で勝負し、 得乗寺の住職が勝って持ち帰った。とか、赤松円心の孫が建てた浜御殿・江林庵 (こうりんあん)現在の得乗寺に献上品として植えられた。ともいわれます。 この栗の木は和泉式部を雨の難儀から救ったというところから、『災難よけの栗の木』と して珍重され、江戸時代には『業(なりわい)の木』として商売繁盛のご利益のある木と されていました。 |
|
|||||
  得乗寺の枝垂れ栗 夏と冬 |
||||||
 枝垂れ栗の木から赤松則祐が彫刻したという久利恵比寿 | ||||||
昔はこの久利恵比寿を祀り、和光楽が舞われる華やかな栗祭が催されていました。
参考資料:相生市立図書館 郷土史の棚の多くの書籍より




