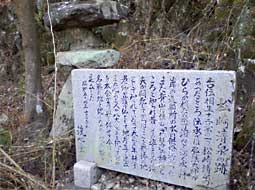|
古墳や窯址の出土品は相生民俗資料館か有年考古館で見ることができます。
※文章は「相生ふるさと散歩」から転載しています。
|
|
相生・野瀬・坪根地区
| 相生天満神社 あいおいてんまんじんじゃ |
| 祭神 |
菅原道真 すがわらのみちざね |
| 由緒 |
海老名家季陣中に道真の像を得、建久二年(1191)九月一社を建立、これを奉祀すると伝えられる。 |
| 境内社 |
三神社 祭神:天照皇太神・稲倉現神・大物主命 |
| 金毘羅神社 祭神:祭神は薬叉神であったが、明治元年の神仏分離令により、祭神を大国主命とした。 |
| 住所 |
兵庫県相生市相生1丁目7-1 |
| |
|
| 相生蛭子神社 あいおいえびすじんじゃ |
| 祭神 |
蛭子命 えびすのみこと |
| 由緒 |
商売の神として信仰の厚い蛭子神社は、寛文五年(1665)海老名家次の建立といわれる。 |
| 境内社 |
住吉神社 祭神:三筒男之命 |
| 海神社 祭神:表津少童命・底津少童命・中津少童命 |
| 住所 |
兵庫県相生市相生2-10-15 |
 |
|
| 相生大将軍神社 あいおいだいしょうぐんじんじゃ |
| 祭神 |
源頼義・義家・頼朝 |
| 由緒 |
創建年不詳、外から入ってくる邪気や災疫を塞ぐ為に藩境や郡境の位置に建立されたと思われる。 |
| 住所 |
兵庫県相生市川原町2-15 |
|
| 天白神社 てんぱくじんじゃ |
| 祭神 |
造化三神=
天之御中主命 あめのみなかぬしのかみ
高皇産巣日命 たかみむすびのかみ
神産巣日命 かみむすびのかみ
工匠祖神=伊斯許理度売命 いしこりどめのみこと (石凝姥命)
海上守護神=
表筒男命 うわつつのおのみこと
中筒男命 なかつつのおのみこと
底筒男命 そこつつのおのみこと
息長帯日売命 おきながたらしひめのみこと(神功皇后) |
| 由緒 |
当時村長だった唐端清太郎氏の要請によって、泉州堺の住人で自ら天白山人と名乗っていた中堀嘉為氏が勧請した。 |
| 住所 |
兵庫県相生市相生5292(IHI内) |
|
| 相生荒神社 あいおいこうじんしゃ |
| 祭神 |
素盞鳴命 すさのおのみこと |
| 由緒 |
創建年月日不詳 |
| 住所 |
兵庫県相生市川原町3-37 |
 |
|
| 青曜山 光明寺 こうみょうじ |
| 本尊 |
阿弥陀如来 |
| 縁起 |
開基は十四代・海老名家季こと道誓、明応五年(1496)。
寛正六年(1465)蓮如上人が寺名をつけたといわれる。 |
| 寺宝 |
絹本墨画松竹図・紙本墨画山水人物鷺図・紙本墨画高士図 |
| 住所 |
兵庫県相生市相生3-7-5 |
|
| 金龍山 親盛寺 きんりゅうざん しんせいじ |
| 本尊 |
観世音菩薩 脇士:弘法大師・不動明王 |
| 縁起 |
三代海老名盛重のとき、建久三年(1192)三月、先祖伝来の帰依仏夢のお告げによって金龍山に親盛寺を建立する。 |
| 境内 |
地蔵尊・ミニ八十八ヶ所巡礼 |
| 住所 |
兵庫県相生市相生4-5-4 |
 |
|
| 城山 じょざん |
大石良雄は地行地の相生をしばしば訪れ、余暇を楽しんだといわれる。
龍山に登り、また海老名邸で休養したといわれている。
現在は龍山公園とよばれている。 |
| 住所 |
兵庫県相生市相生字龍山 |
|
| 市五郎椿 いちごろうつばき |
専修念仏者市五郎ゆかりの椿で年に二度咲くといわれる。
金龍山 親盛寺の裏山(龍山公園)を登ると樹齢三百年以上の椿の巨木がある。
餅屋市五郎は正徳年間に相生に生まれ、親鸞聖人の教えを深く信じ、冬に供える為の椿の木を植える。 |
| 住所 |
兵庫県相生市相生字龍山 |
 |
|
| 天下台城址 てんかたいざんしろあと |
赤松氏が那波野の山の砦と相生村との間の天下台山麓に築いたもので、宇野氏兄弟が備前の児島へ遷ったため、赤松氏の家臣の海老名弾正忠の居城となる。
嘉吉の役において足利市に攻められ落城した。また月見城ともよばれる。 |
| 住所 |
兵庫県相生市相生字天ヶ代5335 |
|
| 北坂地蔵 きたさかじぞう |
| 天明七年(1787)の飢饉による家潰騒動により、頭取とされ相生北坂峠で獄門にかけられた九助の菩提を弔うため、村人たちが建立した。 |
| 住所 |
兵庫県相生市川原町字焼山 |
|
| 松の浦の地蔵 まつのうらのじぞう |
| 天保九年(1838)の建立。いったいは立像で、当時の唐土屋宗太郎が子育て地蔵として建立したといわれる。 |
| 住所 |
兵庫県相生市相生1丁目 |
|
| 海老名家季の墓 えびないえすえのはか |
| 播磨初代海老名家季の墓は相生の小山(元は寺山といい光明寺の持山)にある。 |
| 住所 |
兵庫県相生市川原町字焼山 |
|
| 大石良雄別邸跡 おおいしよしおべっていあと |
相生村を知行地とした大石良雄(内蔵助)は、相生をしばしば訪れ庄屋海老名邸で滞在した。海老名家では西隅に十畳二間をしつらえ大石をもてなした。のちこれを大石別邸と呼ぶようになった。
しかし、海老名家は明治二十七年十一月十七日火災により全焼し、今は庭園にあった池が残っているのみである。 |
| 住所 |
兵庫県相生市相生2丁目15-26 |
|
| 滴水庵 てきすいあん |
| 元大石別邸といわれた海老名家跡に、裏千家浜本氏の寄付により茶室が建築された。適水庵と名づけて市民の利用に供している。 |
| 住所 |
兵庫県相生市相生2丁目15-26 |
|
| 延命地蔵 えんめいじぞう |
| 高取峠の頂上近く旧高取峠の山道にある。別名「いわぬ地蔵」といわれ、その昔悪事を働いた男が地蔵に口止めをした。地蔵が「わしも言わぬがお前も言うな」と答えた。だが男自らが喋ってしまった為に捕まったという話が残っている。 |
| 住所 |
兵庫県相生市相生5306−9 |
 |
|
| 千尋荒神社 ちひろこうじんしゃ |
| 祭神 |
素盞鳴命 すさのおのみこと |
| 由緒 |
創建年月日不詳 |
| 住所 |
兵庫県相生市千尋町18-22 |
| |
|
| 千尋の狩座 ちひろのかりくら |
| 昔、千尋(昔は千色といった)で狩が度々行われたが、浅野公が佐方で狩座を設けた際、狩に使用する道具をあずけた小屋が置かれ、これを守る人が住んでいたといわれる。今でもこの守をしていたという家が代々残っているという。 |
| 住所 |
兵庫県相生市千尋町 |
|
| 壺根金刀比羅神社 つぼねことひらじんじゃ |
| 祭神 |
大物主命 おおものぬしのみこと |
| 由緒 |
創建年月日不詳 |
| 住所 |
兵庫県相生市相生坪根字大谷 |
|
| 壺根遺跡(古墳公園) つぼねいせき |
| 時代 |
縄文後期~古墳後期 |
| 遺物 |
須恵器片、ガラス玉、鉄刀子、勾玉、青銅鏡ほか。 |
| 住所 |
兵庫県相生市相生坪根大谷 |
|
| 鰯浜荒神社 いわしはまこうじんしゃ |
| 祭神 |
素盞鳴命 すさのおのみこと |
| 由緒 |
創建年等不詳。 |
| 境内社 |
稲荷神社 祭神:倉稲魂神 |
| 住所 |
兵庫県相生市鰯浜字立子山 |
|
| 大悲山 願船寺 だいひざん がんせんじ |
| 本尊 |
阿弥陀如来 |
| 縁起 |
天明三年(1783)創建。 |
| 住所 |
兵庫県相生市相生5053 |
|
| 君島 きみじま |
万葉の岬から見える。島の中央がたつの市室津との境界になっている。
その昔、屍島と呼ばれたが、これは室津の遊女の屍が流れ着いたところから呼ばれたらしい。また鳴島とも呼ばれ、この島の頂上をふむと「どんどん」と音がするといわれる。 |
 |
|
| 鬘島 かづらじま |
| 相生湾の入り口に浮かぶ”かづら島”通称「おわん島」と呼ばれている。お椀をふせた様に見えるのでこう呼ばれるようになった。また「ごはんさん」とも呼ばれる。 |
 |
|
| 野瀬賀茂神社 のせかもじんじゃ |
| 祭神 |
別雷神・高龗神 わけいかづちのかみ・たかおかみのかみ |
| 由緒 |
|
| 境内社 |
八幡神社 祭神:誉田別命 |
| 白髪神社 祭神:猿田彦命 |
| 皇神神社 祭神:須佐之男命・大山祗命 |
| 稲荷神社 祭神:宇迦之御魂神 |
| 貴布弥神社 祭神:岡象女神 |
| 住所 |
兵庫県相生市野瀬15 |
|
| 篠村山 誓願寺 せいがんじ |
| 本尊 |
阿弥陀如来 |
| 縁起 |
明治二十五年開基。 |
| 寺宝 |
高雄山観音庵の観世音菩薩 |
| 住所 |
兵庫県相生市野瀬161 |
|
| 野瀬一・二号墳 のせいち・にごうふん |
| 時代 |
古墳後期 |
| 遺物 |
不明。墳丘は大半がなくなり、石室も半壊。 |
| 住所 |
兵庫県相生市野瀬15(賀茂神社裏) |
|
| 平家落人の里 へいけおちうどのさと |
| 建久年間に平盛高の死後、その後室の賤野の方は遺児三人と従者四人、その他三人を伴って、野瀬部落に隠れ住んだといわれる。源氏の捜索を遁れるため、母方の藤原姓を名乗った。そして食糧自給のためこの土地を開いた。それが今に伝わる小字名「七垣内」。七垣内とは「西垣内」「下垣内」「中垣内」「紺屋垣内」「小坪垣内」「寺内」「御坊垣内」の七つで石垣と竹垣によって区画し、東の入口を大木戸、西の入口を谷口とよび砦の形をとっていた。三児と従者四人をそれぞれに分居させていた。 |
| 住所 |
相生市野瀬 五六見山 |
|
| 松崎の清泉 まつざきのせいせん |
| 弘法大師が室の泊りにおいて夢のお告げにより、この地を訪ね泉をひらいたといわれる。以来、磯辺を行交う人々や舟人の水の補給地としてきちょうなそんざいであった。この泉の守護神はうわばみといわれる。 |
| 住所 |
相生市野瀬字猪獅子 野瀬公園そば |
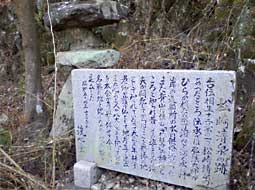 |
|
| 松崎の地蔵 まつざきのじぞう |
| うわばみの出現を恐れる村人のことを嘆かれ松本弥治右衛門はこの地に地蔵尊を建立した。 |
| 住所 |
相生市野瀬字猪獅子 野瀬公園そば |
|
| 八大龍王神 はちだいりゅうおうじん |
| この地の磯辺に住んでいた女性が龍神の化身が枕元に現れ、千年前からこの地に八大龍王神を勧請するように告げているが誰も悟ってくれないのでこの女性に告げているのだといわれ八大龍王神を祀ることになったといわれている。 |
| 住所 |
相生市野瀬字猪獅子 野瀬公園そば |
 |
|
| 小丸一・二号墳 こまるいち・にごうふん |
| 時代 |
古墳後期 |
| 遺物 |
高杯・壺・甕・鉄鏃・鉄刀・水晶勾玉・切子玉・ガラス玉ほか。
調査後、墳は消滅。 |
| 住所 |
兵庫県相生市野瀬字小丸 |
|
旭・那波・竜泉地区
| 厳島神社 いつくしまじんじゃ |
| 祭神 |
市杵嶋姫命 いちきしまのひめみこ |
| 由緒 |
三代・海老名盛重のとき、城内鎮護の為に文治三年(1187)大島の南孿島に弁才天を勧請する。 |
| 住所 |
兵庫県 相生市旭3-1-27 |
 |
|
| 円覚院 (馬通山 円覚寺) えんかくいん |
| 本尊 |
僧都円空法師 |
| 縁起 |
その昔、魚屋の円吉さんが大峰山へ行き円覚僧上となったといわれる。 |
| 住所 |
兵庫県相生市旭5-18-1 |
|
| 箆島 のじま |
| 野島とも書き竹島とも呼ばれる。その昔、矢竹が生えていたのでこの名がつけられたという。今は相生大橋の架橋で島中央が削られ昔の面影はない。 |
| 住所 |
兵庫県相生市旭1丁目 |
 |
|
| 孿島 ふたごじま |
孖島・二子島・双子島と書かれている。
今は埋め立てられて陸続きになっている。二つの島のうち南の島の厳島神社が名残を残す。 |
| 住所 |
兵庫県相生市旭3丁目 |
|
| 唯然地蔵 ゆいぜんじぞう |
| 孫七山山麓に祀られている。明治の終わり頃通行の安全を祈願して、全国四万八千体の地蔵建立の運動が高まり、相生の浜本氏の尽力で五体が造られ、その一体が昭和三年( 1928 )ごろこの地に安置された。 |
| 住所 |
兵庫県相生市旭5丁目15 |
 |
|
| 中央通の楓並木 ちゅうおうどおりのかえでなみき |
| 昭和三十四年(1959)北朝鮮へ帰る人々が中心となり、在日の記念に植樹したもの。 |
| 住所 |
兵庫県相生市旭5丁目15 |
|
| 那波八幡神社 なばはちまんじんじゃ |
| 祭神 |
応神天皇 おうじんてんのう |
| 由緒 |
文治年間(1185~1190)に勧請、創立不詳。天明二年(1782)再建。 |
| 境内社 |
高良神社 祭神:武内宿弥 慶応四年(1868)創建。 |
| 稲荷神社(松尾稲荷) 祭神:宇迦之御魂神 明治四十年(1907 )大島山頂より移される。 |
| 住所 |
兵庫県相生市那波本町17−30 |
 |
|
| 那波荒神社 なばこうじんしゃ |
| 祭神 |
素戔嗚命 すさのおのみこと |
| 由緒 |
創建年不詳。文禄年間(1592~1596)残留六家の氏神として祀った地蔵尊とも、文禄・慶長年間(1596~1615)における浜神殿開拓の際に掘り出した地蔵尊を祀ったものともいわれる。 |
| 境内社 |
稲荷神社 祭神:倉稲魂命 明治五年(1872)創建。 |
| 住所 |
兵庫県相生市那波本町4-30 |
|
|
| 天照(正)岩 てんしょういわ |
| 山腹に見える岩は保元二年(1157)伊予水軍の越智通清が荒神山へ三島神を遷座した際、この岩に流星が落ちたところから天照岩とよばれ、また天正年間に豊臣秀吉が播磨地方を攻勢したとき、この岩の上で指揮をとったといわれる。 |
| 住所 |
兵庫県相生市那波本町 |
|
| 那波大避神社 なばおおさけじんじゃ |
| 祭神 |
秦河勝 はたのかわかつ |
| 由緒 |
創建年不詳。秦河勝は海路那波の津に入り、白鷺の鼻(那波大避神社がある場所)に住んでいた。後世において河勝の住んでいた場所に大避社を建立した。 |
| 住所 |
兵庫県相生市那波南本町9-8 |
 |
|
| 那波住吉神社 なばすみよしじんじゃ |
| 祭神 |
三筒男之命 みはしらのつつのおのみこと |
| 由緒 |
寛正五年(1464)創建。天保十一年(1840)再建。
明治初期に大島へ遷座。 |
| 境内社 |
稲荷神社 祭神:倉稲魂命 文久二年(1862)創建。
明治初期に大島へ遷座。 |
| 金刀比羅神社 祭神:大物主命 慶応元年(1865)創建。
|
| 住所 |
兵庫県相生市那波大浜町25-11 |
 |
|
| 三宝荒神社 さんぽうこうじんしゃ |
| 祭神 |
三宝荒神 さんぽうこうじん |
| 由緒 |
通称「豆煎荒神」。代々岡田家の荒神といわれる。その昔、神宮皇后新羅への征進に際し、先鋒の将千宿称三並をして赤地の鼻に三島大神の分霊を鎮祭した。のちこれを荒神山に移し、保元二年(1157)再建した。 |
| 境内社 |
國光稲荷神社 祭神:國光稲荷大神 |
| 妙見社 祭神:
|
| 大石内蔵助が奉納したといわれる手水鉢
|
| 参道に江戸くだりの記念に浅野内匠頭が手植した義笹が茂る。 |
| 住所 |
兵庫県相生市那波本町字上ノ山 |
 |
|
| 國光稲荷神社 くにみついなりじんじゃ |
| 祭神 |
國光稲荷 くにみついなり |
| 由緒 |
保元二年(1157年)河野通清は神託を受け、國光稲荷という名前をつけた社を建て 那波浦丘の台を前殿とし、金剛山天下台山頂の洞窟を奥殿として祀った。 天正七年(1585年)に羽柴筑前守秀吉は、越智播磨守と戦い、これにより那波浦丘の台にあった國光稲荷社は戦火に巻き込まれ、社堂と共に古記録・文書・宝物などおびただしい量が灰となった。
この始末に恐れた秀吉は天正七年十月二十五日、加藤清正を使者とし、『最上位 國光稲荷大神』との尊號を奉献した。
また浅野内匠頭は家臣の武林唯七と神崎与五郎に代参させていた。神埼与五郎は母親の目の病を治す祈願をしたところ、國光稲荷大神が現れ療法を教えたといわれる。 |
| 境内社 |
三宝荒神社 祭神:三宝荒神 |
| 妙見社 祭神:
|
| 大石内蔵助が奉納したといわれる手水鉢
|
| 参道に江戸くだりの記念に浅野内匠頭が手植した義笹が茂る。 |
| 住所 |
兵庫県相生市那波本町字上ノ山 |
 |
|
| 江林山 得乗寺 こうりんざん とくじょうじ |
| 本尊 |
阿弥陀如来 |
| 縁起 |
文明十六年(1484)開基。赤松円心の六男持則が僧となり、その後永禄五年(1563)山・寺号を許可される。 |
| 境内 |
和泉式部ゆかりの枝垂れ栗の木がある。 |
| 住所 |
兵庫県相生市那波本町17-21 |
 |
|
| 大島山 善光寺 おおしまさん ぜんこうじ |
| 本尊 |
一光三尊善光寺如来 |
| 縁起 |
室町時代 赤松円心家臣の海老名家の山城、大島城跡に海老名家の菩提寺として、建立された。
昭和3年には信州善光寺より御本尊の御分身をうけて、寺号も善光寺を名のる。 |
| 境内 |
ミニ西国三十三ヶ所巡礼 |
| |
石の弘法大師(首飛ばしの弘法大師) |
| |
家内安全のお大師さま |
| 住所 |
兵庫県相生市那波大浜町25-11 |
| |
|
| 那波丘ノ台城址 なばおかのだいしろあと |
| 現在は那波中学校テニスコートになっている。 |
| 住所 |
兵庫県相生市那波南本町5−44 |
|
| 神崎与五郎宅 かんざきよごろうたく |
| 赤穂義士のひとり、神崎与五郎が住んだとされる家は、元丘だけの家来長屋の一角にあり現存の「神崎与五郎孝行井戸」の脇の家がそれといわれる。 |
| 住所 |
兵庫県相生市那波本町 |
|
| 大島城址 おおしまじょうあと |
播磨初代海老名家季の築城といわれる。標高三四・五メートルで遺構として東側に犬走りが幅四メートルほど残っており、北側には三段階の腰曲輪と帯曲輪が認められる。善光寺背後には中世のものと見られる五輪塔・宝篋印塔がみられる。
城で利用されていたと思われる井戸はいぼ取り井戸といわれる。 |
| 住所 |
兵庫県相生市那波大浜町25-11 |
 |
|
| 大島の地蔵尊 おおしまのじぞうそん |
島の北側山麓に数体の地蔵が祀ってある。右側の地蔵は善光寺旧参道の石仏と同じ大正年代に建てられたもので、左側は高取峠にあったものを移したといわれる。
眼病をわずらった婦人が参詣のおかげで眼病が完治した。高取峠まで参拝に行くのは不便なのでこの地に移したという。 |
| 住所 |
兵庫県相生市那波大浜町25−11 |
 |
|
| 苧谷川・普光沢川・鮎帰川 おこくがわ・ふこさがわ・あいかえりがわ |
| 苧谷・鮎帰川は源流を光明山に、普光沢川は原大池から流れている。川名の苧谷は苧(からむし)の生産が行われていた那波新田一帯、鮎帰は鮎狩りが出来たといわれる川から、普光沢はあまねく光るさわであったのでその名がつけられたといわれる。 |
|
| たんたん通り たんたんどおり |
昔、三木家と田中家の間は人が一人と折れるほどの細い小道で、通ると「たんたん」と音が響くのでこの名がついた。たんたん通りに鬼が出るという話もあった。
現在は両家ともなく、広い道になっている。 |
| 住所 |
兵庫県相生市那波本町16−9 |
|
那波野・古池・陸地区
| 陸荒神社(陸天満社内) くがこうじんしゃ |
| 祭神 |
|
| 由緒 |
嘉吉の乱(1441)において越智通祐が戦死したので宇陸の西南の丘に埋葬した。また討死した武士の霊を合祀し、陸荒神堂とした。 |
| 住所 |
兵庫県相生市陸811 |
|
| 狐塚古墳 きつねづかこふん |
| 時代 |
古墳中期 |
| 遺物 |
玉類・鏡・武具・馬具(現在消失)鉄鎖・金銅杏葉・銅鈴・きぬがさ形埴輪ほか。
現在墳は消滅碑が建てられている。 |
| 住所 |
兵庫県相生市陸本町1−7 |
 |
|
| 陸構谷古墳 一・二号墳 くがかまえたにこふん |
| 時代 |
古墳後期 |
| 遺物 |
金環小玉・提瓶・壺・杯ほか。現在墳は消滅。 |
| 住所 |
兵庫県相生市陸構谷 |
|
| 光明山城址 こうみょうせんじょうあと |
| 建武年間に赤松則村によって築城される。矢野町二木に抜ける林道が開通している。 |
| 住所 |
兵庫県相生市陸字光明山 |
|
| 笹尾城址 |
| 陸と揖西町竹原の境界の尾根に存在が明記されており、曲輪跡とみられる削平地が見られる。 |
| 住所 |
兵庫県相生市陸字光明山 |
|
| 池ノ内荒神社(陸天満社内) いけのうちこうじんしゃ |
| 祭神 |
天照大神・産土大神 あまてらすおおみかみ・うぶすなのおおみかみ |
| 由緒 |
安政四年(1857)創建。 |
| 住所 |
兵庫県相生市池之内261−1 |
|
| 遍照山 長恵寺 ちょうけいじ |
| 本尊 |
阿弥陀如来 |
| 縁起 |
毛利元就の家臣の山本十郎左衛門が病気のため池之内村に居住し、老後剃髪して道珍と名乗り、蓮如上人に帰依して明応五年(1496)一堂宇を建立。
|
| 住所 |
兵庫県相生市池之内591 |
|
| 那波山城址 なばさんじょうあと |
| 承安三年(1173)那波浦の東にある陸村のはずれの丘の上に平経盛が築城したといわれる。寿永の役に源義経が攻落したといわれる。この戦によって平家の残党は赤穂郡上郡町の小野豆に逃れたという。 |
| 住所 |
兵庫県相生市汐見台43−16 |
|
| 神戸若宮神社(子安荒神) かんべわかみやじんじゃ |
| 祭神 |
|
| 由緒 |
天文三年(1535)河本家第九代の源之助が夢のお告げにより石像を得て堂宇を建立したのがはじまりという。延宝三年(1675)京極家の妻の難産に、この荒神の雨だれの砂を床にしいたところ安産となったことから子安荒神というようになった。 |
| 住所 |
兵庫県相生市那波野519−45 |
|
| 岩谷山 西法寺 いわいざん さいほうじ |
| 本尊 |
阿弥陀如来 |
| 縁起 |
稼吉の乱後、赤松氏の一族祐西は実如上人に帰依し、方便方身像を賜り大栄三年(1523)ここに一寺を開基した。山門は元若狭野陣屋の表門である。
|
| 住所 |
兵庫県相生市那波野3丁目10-5 |
|
| 那波野塚森古墳 なばのつかもりこふん |
| 時代 |
古墳中期 |
| 遺物 |
円筒埴輪片・金環・勾玉(伝) 前方後円墳の可能性有り。 |
| 住所 |
兵庫県相生市那波野3丁目字土穴 |
|
| 那波野古墳 なばのこふん |
| 時代 |
古墳中期 |
| 遺物 |
円筒埴輪片・須恵器片・甕 墳丘はほとんどが消滅している。 |
| 住所 |
兵庫県相生市那波野278 相生カントリークラブ内 |
|
| 古池横山一・二号墳 ふるいけよこやまいち・にごうふん |
| 時代 |
古墳後期 |
| 遺物 |
堤瓶・蓋付杯・壺・耳輪・切子玉・土錘・刀剣片・須恵器片ほか。
墳は完全に消滅。 |
| 住所 |
兵庫県相生市向陽台 |
|
| 鱗塚 うろこづか |
| 古池長池の中に石碑が建ててある。天保十年(1839)亥月と刻まれている。池の修理費を捻出するため、この池の魚を取って売りその金で池の修理を行った。魚の供養にと碑を建てたもの。 |
| 住所 |
兵庫県相生市向陽台 長池 |
|
緑ヶ丘・青葉台・佐方地区
| 佐方八幡神社 さがたはちまんじんじゃ |
| 祭神 |
応神天皇 おうじんてんのう |
| 由緒 |
佐方の漁夫が拾った木片に宇佐八幡の文字が現れ、これを奉載して宮の谷に奉祀した。 |
| 境内 |
金刀比羅神社 祭神:大物主命
大避神社 祭神:大避大神
荒神者 :祭神:須佐之男命 |
| 住所 |
兵庫県相生市佐方一丁目3-8 |
 |
|
| 霊松山 慈眼寺 れいしょうざん じげんじ |
| 本尊 |
阿弥陀如来 |
| 縁起 |
天平二年(730)に行基によって開基されたといわれる。
以前は温泉山慈眼寺といい観音菩薩を本尊としていた。 |
| 境内 |
佐方薬師堂 本尊:薬師如来 |
| 佐方観音堂 本尊:聖観音菩薩 |
| 梵鐘 文明七年(1475)美作国上福寺の鐘。市指定文化財 |
| 住所 |
兵庫県相生市佐方1丁目19−9 |
|
| 鍛冶屋 かじや |
| 高取峠の北側、佐方集落の南の山麓に温泉が出ていたという。その昔この地は鍛冶屋が多く、三木市の鍛冶屋は佐方から移住した者だという。 |
| 住所 |
兵庫県相生市佐方 |
|
| 佐方の地名 さがたのちめい |
| その昔、秦河勝が那波の白鷺の鼻に住んでいたときに、佐方の村人に酒の作り方を教えた事からこの名がついたといわれる。 |
| 住所 |
兵庫県相生市佐方 |
|
|
古墳や窯址の出土品は相生民俗資料館か有年考古館で見ることができます。
※文章は「相生ふるさと散歩」から転載しています。 |
|